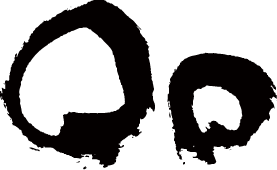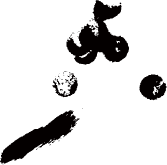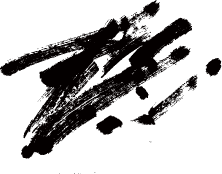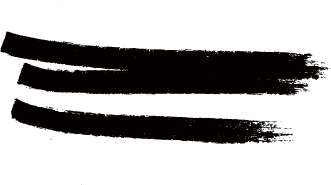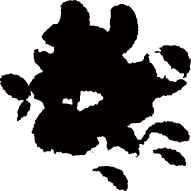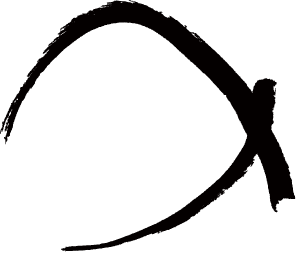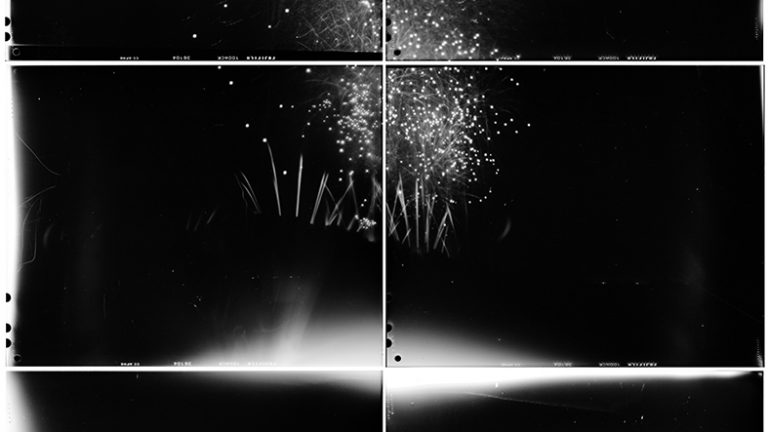062015
Special #6
食べるという行為が見せてくれる風景
山フーズ主宰 小桧山 聡子氏インタビュー
食は、年齢も性別も国籍も問わない、
すべての人にとっての共通言語であり、体験だ。
食は、いつだって人の興味の中心にある。
そんな食と幼い頃から向き合い、
現在「山フーズ」として
様々な表現活動を行う小桧山聡子さん。
彼女の活動を通じて、私たちは新しい食の風景を垣間見る。
真夜中のキッチンとポトフ
そもそも小桧山さんにとって、今の活動の原点とはなんですか?
料理好きの母の影響が大きいです。昔、母はケータリングのような事をしていた時期があって、私自身も、幼稚園に通い出した頃からよく一緒に台所に立っていました。包丁持って、母の隣で料理するのがとにかく楽しかったですね。以来、料理をすることは私にとって日常の一部になっていったんですけど、その日々のなかで自分なりにいろんな視点から食を突き詰めていくうちに、最終的には食べるという行為、体感に興味を持ち始めたんです。
行為、体感。そこに興味を持つ、きっかけについて教えてください。
ある日の深夜、家族が寝静まった自宅のキッチンに立ったときに、ポトフの入った鍋が置いてあったんですね。その鍋を見た瞬間に、「鍋のなかに手を突っ込んでみたら、どうなんだろう?」って、ふと思って。それで実際に手を突っ込んで、なかに入っている肉を掴んで食べてみたんです。そうしたら、普段食べ物を食べているときの感覚とは全然違う、今までにない感覚が、自分のなかに広がっていって。
突っ込んでみようと思う視点と行動力が、すごい(笑)。人間の野生を感じます。
そうですか?(笑)。まずやってはいけないことをやってしまった、という快感がすごくありました。料理の入った鍋のなかにお玉も使わず手を突っ込んだわけなので。また、誰もいない暗く静まりかえったキッチンで掴んだ肉の手触りと、食べたときの口の中の食感、自分の咀嚼する音どれもが鮮明に響いてきてはっとしたのを覚えています。肉を食べているという実感がいつもよりリアルで、食べるってものすごく沢山の感覚を使う豊かな行為なんだと再認識した瞬間でした。


その体験をきっかけに、食べるという行為、体感を突き詰めるようになっていったんですね。
はい。例えばお皿に乗った食パンを寝転んだ状態で食べたらどうなんだろう?とか、この気分の中で何をどのように食べるのが一番しっくりくるだろうか、とか、それからしばらくはそういうことばかり考えるようになりました。同じ料理でも、食べるシチュエーション、それは食べるときの身体の体調や気分もそうですし、スプーンなのか、箸なのか、手で食べるのか、誰と一緒に食べるのか。そのときの要素によって味の感じ方が全く変わってしまうものだから。要は食べることは、食べ物を口にすることだけじゃなくて、そのまわり、背景の空気も一緒に食べるということだと、実感して。そういうものも含めて、栄養、血肉になっていくんじゃないかと思ったんです。それから、体感の話でいうと食べる、だけでなく料理するということも。いろんな素材を包丁で切ったり、鍋で煮たりする過程もすごくドラマティックで美しい場面がたくさんある。その瞬間、瞬間は台所で起こっていて、食卓にはすべてはのせられないけど、そういった、食べるにまつわるキラキラした瞬間、体感を私はいろいろな形で表現できたらと思っているんです。そういう意味ではテーブルウェアも、私にとっての食べるという体感を楽しむための道具のひとつになりました。調理中に使用する、キッチンタオルもそうですが、テーブルにセットするキッチンクロスの色が変わるだけで、よく作るカレー(写真)の持つ表情も全然違って見えるんです。日常のあたりまえ、になったものを、ちょっと変えてみることで、ワクワクできることって沢山あると思っています。



どんな活動をしても、
食べて美味しいが着地点
小桧山さんは人の本能に関わる部分を、食を通じて探って、表現している感じがします。それは私たちが普段、使っていない、または鈍っている身体性を呼び覚ましているような。その独特な感性は一体どこで育まれたんですか?
それは学生時代(多摩美術大学)に油絵科を専攻して、立体や平面の作品を制作したり、舞踏、コンテンポラリーダンスをやっていたことも大きく影響していると思います。要は“身体”そのものに興味があって、自分自身のテーマも、ずっと身体から離れなかったんですよね。
現在、山フーズとしてはどんな活動がメインになっているのですか?
主にケータリングの仕事が多いです。ただ、私自身がこういうちょっと変な考えを持って食と向き合っているので(笑)、ケータリングと言っても、求められるコンセプトが一風変わっていたり、その料理の提供の仕方から企画して作り上げることもよくやらせていただいています。それは例えば空間の演出だったり、料理を盛る什器やメニューのデザインだったり……。だから難しいオーダーをいただくと燃えますね(笑)。あとは、雑誌や広告の撮影のスタイリングや、子供向けの食のワークショップもやらせていただいています。ワークショップは、例えば食べられるお皿を作って料理を盛り付けて、お皿まで全部食べてもらったり、料理教室というよりは、食べる体感を普段とは違う角度から味わってもらうような内容になっています。
今後、挑戦したいことがあれば、ぜひ教えてください。
料理は食べる直前が完成品で、そこから食べ進めていくうちにその完成品は壊されていきますよね。そういう視点から見ると、例えばケータリングでも、料理が出されたあとに遅れて会場に来られた方は、その完成品を見て食べていただくことができない。そのことが私の中でずっともやもやしていて。で、あるときふと思ったんです。食べ終わったお皿を見てきれいだなって思う、その感覚をうまく表現できたら可能性が広がるかもしれないと。それでパフォーマンスとして、料理の盛り付けをお客様の前で行って、そこで出来上がったもの食べていただく。そして食べ進めると、その食べ跡が絵になっている。というようなケータリングを最近よくやっていたりしていて。この行為をもっと突き詰めていきたいなって今は思っています。自分自身もやっていてドキドキできるような、新しい食の切り口を模索し続けていきたいなと思っています。
お話を伺っていて、いろんな人に小桧山さん、山フーズの表現を、それこそ「体感」して欲しいなって強く思いました。
こうやってお話していると、結構奇抜なことをやっているなって感じられる方も多いと思うんですけど、私のなかで山フーズとして活動するときに、ひとつ絶対条件にしていることがあるんです。それは「美味しい」ということ。どんなに奇抜に見える完成品(料理)でも、食べて美味しいというのが着地点じゃないと、私が活動する意味はないなって思っています。「料理して食べる」という行為には、最大限の敬意を持っていたい。
作る過程で一番気にする事は、食材本来の持つパワーや、料理としての勢いやオーラみたいなものを汚さずに、どうバランスをとるかということ。単に、コンセプトや表現の為のツールとして食材を利用する、みたいなことは無いようにといつも心に留めています。そこだけはこれからもぶれずに、いろんなことにチャレンジして行きたいです。


小桧山 聡子
1980年東京生まれ。多摩美術大学油画専攻卒業。在学中は金属や布を用いた立体作品、身体表現、平面作品などを制作。現在は、「食とそのまわり」を独自の視点で発信する「山フーズ」を立ち上げ、ケータリングやイベント企画、ワークショップ、レシピ提供、コーディネートなど様々な角度から食の提案を行っている。