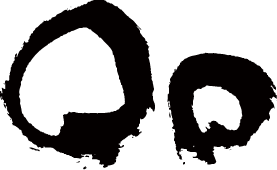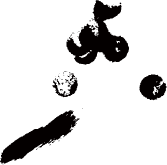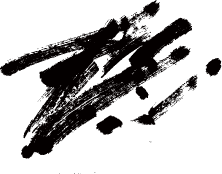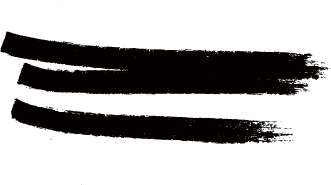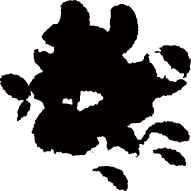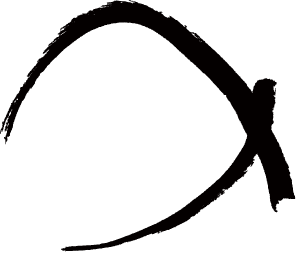ルイ・アラゴン、あるいはシュールレアリズム文学。
ルイ・アラゴンはフランスの詩人にして小説家。シュールレアリズム運動の提唱者アンドレ・ブルトンと並んでシュールレアリズム文学の牽引者である。
シュールレアリズムとは直訳すれば超現実主義であり、夢(空想)と現実の境を行き来する人間の意識の革命であり冒険の運動でもある。それはまた心理学者フロイトの夢の理論の芸術的実践でもあり、世界はこのようにあるべきものだという理想主義とはことなり、ある意味場当たり的な出来事であったり、ふいに口をついて出る言葉など、偶然さえも必然であると認めることであったりする。そしてそれは写実的であったり、合理主義、リアリズムであったりとこの世の中にある、そのありようとはことなるところの意味において芸術家のありかたのその直感と主観の上に成り立っている。そしてそれはまた現実の世界を否定した上での空想主義ではなく、世界のありよう、人間のありかたそのものから生じた、現実とは相容れないかたちでの<超現実>なのだ。
「イレーヌ」は1928年「Le con d’irene」というタイトルで(意味は書けないので気になる方はググってください)150部限定作者不明のまま地下出版されており、同じパリの出版社から同年上梓されたフランスの思想家ジョルジュ・バタイユの「眼球譚」(これも当初ロード・オーシェの偽名で出版されている)とその装丁、内容共に対をなすものである。ちなみに挿絵は共にアンドレ・マッソン(1947年発行の改訂版にはドイツの人形作家で画家のハンス・ベルメールの美しい線描画が収められている)。その文体は耽美的で自動記述的であり(オートマティスム)、シュルレアリズム、エロティシスムの境界を自由に往来し(そもそもエロティシスムとシュールレアリスム的要素はフロイトの理論においてはまさしく隣人である)、ときにアルチュール・ランボーであったりロートレアモンであったり盟友ブルトンであったりと、シュールレアリストたちの偉大なる先駆者達の言説をなぞりつつ、言葉の濁流とでもいえるように展開されていくありえない物語はまさに<超現実>的である。
小説「オートバイ」で高名なマンディアルグはこの本の新装版の序文において作者の謎に触れ、あくまでこの天才的な文体は同じシュールレアリストであるルイ・アラゴンその人であると推測する。その後晩年においてもアラゴン本人はこの超現実小説が自分の作品であることを認めていない。しかし世界の文学界においてはもはやこの書物は作者ルイ・アラゴンでありこの天才以外の人物がこのような書物を著せないであろうことは誰もが知るところとなっている。日本語訳者はフランス文学の名訳者にして詩人の生田耕作、生田もこの本のあとがきで謎の作者について触れており、あの植草甚一が自著「ポルノグラフィー始末記」においてイレーヌの作者について、アラゴンその人でないと述べていることについて、ありえないでっち上げ、と反論しているところが興味深い。そしてこの書が上梓された1928年はフランス文学にとっての素晴らしき一年であり、この同じ年に上梓された書物にはブルトンの美しい書物「ナジャ」がある。そしてシュールレアリズムの活動がダダイズム以降であることも興味深い事実である。ドイツを中心に発生したこの芸術活動は合理主義に反旗をひるがえすところの反芸術活動であり、<ダダ>という言葉が無作為に選ばれた、その活動とは何の繋がりも持たないフランス語の「木馬」を意味するところからもその反逆精神を理解する事ができる。芸術的活動としてのダダはパリを中心に展開され、ピカビア、デュシャン、当時パリに滞在中のマン・レイなどを巻き込みながら拡大していく。実際アラゴンもダダの詩人としてパリの文壇に登場している。ダダは1924年のブルトンによる「シュールレアリズム第一宣言」によってその活動を終結するわけだが、主要人物たちはその後シュルレアリズムの名の下に活動していくことになる。
ダダイズムとシュルレアリズムは一つの系譜上に連なる思想的に同じ運動なのである。
1930年代後半シュールレアリスムの活動はナチスの台頭により終焉をむかえるが、その精神は今なおそれを見るものに新鮮な驚きと創造力を喚起させるだけの力を備えている。