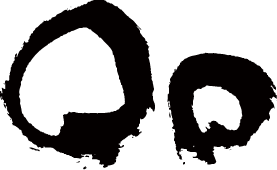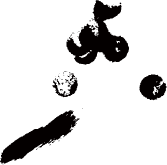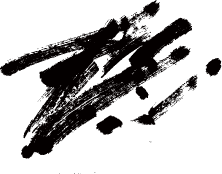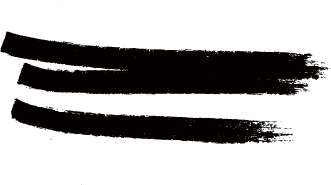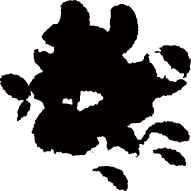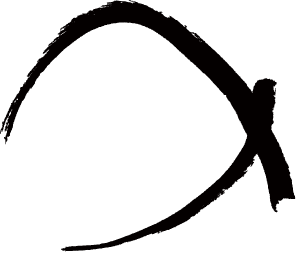仏教の入り口がひらいた。
先日、大阪で音楽家の友人のライブを目撃したのち、私は久しぶりに京都で一泊することにした。
大きな目的は持たず、心のままぶらぶらしようと決めていた京都。とはいえ以前から関心のあったお香のお店、唐紙師のお店、お菓子屋さん、喫茶店などは立ち寄ってみようとは思っていたし、実際、休業だった喫茶店をのぞいて、全て足を運ぶことができて心満たされた。その上でまだ時間に余裕はある。であるならせっかく京都に来たのだからと、ひとつくらいお寺を見て帰りたいと思った。ホテルに置いてあった京都観光ガイドを見ながらたまたま目に入ったのは、法然院「秋季 伽藍内特別公開」の文字。法然院とは、鎌倉時代初期に活躍し、専修念仏で知られる法然上人ゆかりの寺だ。ちょうど私が京都にいるこの日も特別公開期間中であった法然院に、早速訪れることに決めた。
「紅葉シーズンでも法然院は比較的静かなお寺ですよ。お客さん、知ってますか?清水寺の入場者は、ディズニーランドの入場者数より多いんですよ」。あの広大な敷地を持つディズニーランドよりも清水寺に人が集まっているなんて。向かう途中のタクシーの運転手さんの発言に驚いているあいだに、法然院にたどり着いた。
苔むした茅葺屋根の周囲を囲む木々の葉の先端が、少しだけ赤く染まっている。この風景が真っ赤に染めあがるには、あと2週間ほどかかるだろうか。私はゆっくりと足を進めながら、伽藍内へと向かった。そこで見た風景、過ごした時間。これまで様々なお寺に足を運んできたけれど、そのどこでもない深い体験、腑に落ちる感覚。言葉ではいい表せないその体験を通して、私は人生で初めて仏教が自分ごととして迫ってきたような気がした。
「修行しても煩悩を抑制できない我が身は、地獄へ住くしかない」。比叡山で苦しんでいた親鸞は山を下り、法然の弟子となっていたこと。「生涯、人間は自己中心性から逃れることができないが、自身が自己中であることをよく自覚して生きることが大切」だと、法然と親鸞は説いてきたこと。そしてそんなふたりの仏教の概念を、現代社会に生きる私たちに伝わる言葉で翻訳し続けて来た現・法然院貫主・梶田真章氏。「人は、因縁が整えば何を仕出かすか、どんな目に遭うか分からない哀しい生き物である。この世では時として不条理に出合うからこそ、宗教は必要とされたきた(*1)」。「〜良きにつけ悪しきにつけ、すべて私の業縁であって、それを引き受けていく、という覚悟していくことの中に、他力(たりき)の理解が生まれてくるのだと思います(*2)」。
仏教をもっと知りたい。梶田貫主の視点を通して、世界を見てみたい。その入り口がひらいたような、そんな気がした。帰り際、木々の紅葉が少し進んだ気がしてしまったのは、やっぱり錯覚なのだろうか。
*1 毎日新聞 新聞時評 2010年2月15日の記事より抜粋
*2 梶田真章さんとの対話/無数のいのちの重なりの中に、今ここの「私」がいる の記事(https://temple-web.net/column/389/)より抜粋