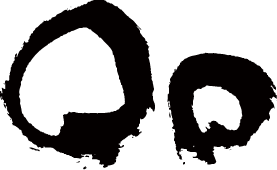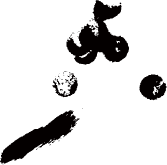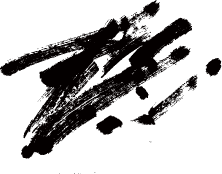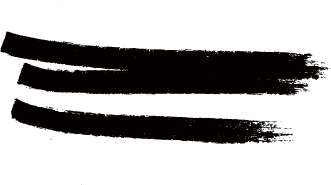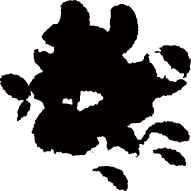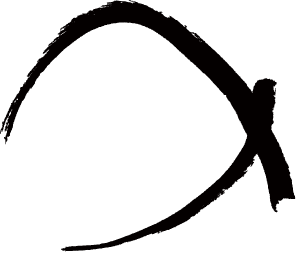072019
Special #36
映画『あなたの名前を呼べたなら』
ロヘナ・ゲラ監督インタビュー
インド社会に未だ根強く残る、身分制度。
この悪しき因習は人を愛するという人間のごく自然な営みすら阻んでしまっている。
そんなインド社会の分断を、身分の違う恋愛を通じて私たちに語りかけているのがロヘナ・ゲラ監督だ。
インドの裕福な家庭で育ちながら、身分制度からくる人々の差別意識に強く違和感を覚え続けた監督が、
本作を通じてインド社会に変革を起こす。
身分の違う恋愛を通じて、
インド社会の分断を見つめる

ラトナ(左)は新婚のアシュヴィン(右)の自宅で住み込みのメイドとして働くはずが、結婚が破談となったことでアシュヴィンとふたり暮らしとなる。
『あなたの名前を呼べたなら』はインド・ムンバイを舞台に、農村出身のメイド・ラトナと建築会社の御曹司・アシュヴィンの恋愛模様を描いていますが、ふたりの恋愛は、インドの身分制度や因習と切り離して捉えることはできません。
身分の違うラトナとアシュヴィンの恋愛を描こうと思ったのは、私自身の実体験として、長く差別や偏見が残るインド社会の分断を見つめてきたからです。幼い頃、私の実家には住み込みのメイドがいました。私は、私の面倒をみてくれていたそのメイドととても親しい仲でしたが、同じ人間としての立場の違いは明らかで、その悲しい記憶がずっと心の真ん中に残り続けていたのです。並行して私は大人になるにつれて、自分が愛そうと選んだ相手を、人はどのように愛するのか、ということを考え始めていました。そういったなかで今回、ずっと心にあり続けたインドの身分制度の問題を、恋愛物語を通じて探求できないかと考えたのです。

現在はフランス在住のロヘナ・ゲラ監督
主人公のラトナは夫を結婚4か月で亡くした未亡人として描かれています。それも、親の都合で不知の病を持った夫のもとへ嫁ぎ、その夫が亡くなったあとは、食いぶちを減らすためにメイドとしてムンバイに出稼ぎに、という背景を持って。ヒンドゥー教は法律上、再婚をすることは認められていますが、作中のラトナは今後、再婚することが困難であるように描かれています。それは暗に、インドの現実社会において、法律はあまり機能していないということを示唆しているのでしょうか?
インド社会においては「それが合法か違法であるか」ということよりも、社会が何を許すのか。ということの方が重要視される傾向にあります。つまり、法律よりも社会的圧力の方が強力なのです。もしも未亡人という立場で男性とデートをすれば、社会から白い眼で見られてしまう風潮がまだインドには強く残っていますし、再婚ということでいえば、特に子供がいる女性はいっそう難しい。また未亡人はたとえ実の妹の結婚式であろうと、新婦の前に姿を見せることはできません。サリーの色は制限され、アクセサリーでさえも不謹慎だと非難を浴びてしまうことも。このように、未だインドでは女性のセクシャリティがとても抑圧されているのです。それが現実ですが、だからといって私はラトナを「被害者」として描くことは、絶対にしたくありませんでした。

夢を追いかけるラトナ。劇中、インドならではの色鮮やかなテキスタイルもたくさん登場する。
おっしゃるようにラトナにはファッションデザイナーになるという夢があり、ムンバイはそれを叶えるための舞台でもありました。
女性というのはどんな状況下におかれてもクリエイティブになれるし、自分なりの生き方を見つける力を持っている。私はそう信じているのです。ラトナもまた、そういう力が備わっている女性にしたかった。例え不条理なインドの古い習慣に縛られていたとしても、彼女は日々のなかで笑うことができるし、笑える瞬間を自分で見つけることができる。そういう女性を表現したいと思いながら脚本を書きました。

ラトナの芯の強さは十分に伝わってきました。その一方印象深かったのは、すべてにおいて恵まれているはずのアシュヴィンの方が、身も心も不自由な暮らしをしているように見えたことです。
自分の夢を諦めてアメリカからインドに帰国し、だだっ広い高級マンションに住みながら父親の建設会社を手伝うアシュヴィン。実際、彼のように特権階級に縛られながら、飾られた折の中で生きているインド人は数多く存在しています。
そんなアシュヴィンの日常を、ラトナの存在が少しずつ変えていきますよね。
アシュヴィンはすべてを持っていながら、夢を見ることができず、その夢を諦めてしまっています。一方のラトナは何も持っていないけれど、夢を持ち、夢のために闘い続けている。アシュヴィンはそんな彼女のダイナミズムに惹かれていきます。外見ではなく、女性の内に秘めた強さに惹かれる。男性はそうあって欲しいという(笑)、私個人の願望もどこか込めて描いているところがありました。
インサイダーであり、
アウトサイダーでもある自分

インドの大都市では、裕福な家庭は数人のメイドを雇いながら生活するのが当たり前。メイドの用の小さな部屋が最初から設計されていて、そこでラトナのようなメイドが暮らす。
ラトナとアシュヴィンの関係は、アシュヴィンの高級マンションのなかで描かれています。使用人と雇い主。単調なルーティーンワークの繰り返しで成立しているふたりの距離感が、互いを少しずつ知るうちに、ルーティーンではなくなっていく。その間合いがとても繊細に描かれているのが印象的でした。
そこに気づいてくださって嬉しいです。私自身、ラトナとアシュヴィンの距離感の表現についてはすごく気を使いました。なぜならとてもささやかな形で描いていきたかったから。ふたりは同じ家のなかで過ごしているので、一見すごく近しい距離にいるように思えて、実際にその距離を縮めることは不可能な環境にいるのです。軽く手が触れることすら、許されない。それを皆さんに感じていただきたかった。そのひとつの撮影手法として、例えばトラッキング・ショットを用いました。ふたりがそれぞれ居る空間を横移動しながら撮影したんですね。ふたりのあいだには部屋を仕切る壁があって、その壁は、決して動かすことのできないふたりの距離をあらわしてもいるのです。また距離ということで言えば、劇中、ラトナはトレイを介して水や食事をアシュヴィンに渡すシーンがありますが、それも何気なくふたりの距離感を示しているのです。


確かにラトナはよく物を運んでいました。その物が、ある種のふたりのあいだを隔てるバリアのようなものになっていたんですね。
そうです。渡ることのできない、橋のような存在です。でもその橋がなくなったとき、初めてふたりは自分たちの関係に言い訳ができなくなるのです。ただそのことは、ラトナとアシュヴィンを演じたティロタマとヴィヴェークには事前に説明しませんでした。自意識過剰になってはいけないと思ったからです。
変化していくふたりの関係を観ながら、インドの人たちはこの作品をどのように受け止めるのか、率直に知りたいとも思いました。
現代のインド社会においてふたりのような関係を公にすることは、ほぼ不可能と言えます。もし公になれば、社会から疎外されてしまう可能性が高いです。よってインドの人たちからすれば、ふたりの恋愛は未だ有り得ない物語として映るでしょう。なぜならインドにおいて身分制度からくる差別や偏見は未だ根強く残っているから。私自身はそこに激しく違和感を覚え、社会を少しでも変えたいと願いました。その上で実際にこの作品を作る上では、私自身がインドにとってインサイダーであり、アウトサイダーでもあるという目線が役立ったと思っています。

アウトサイダーの目線はどこで培われたのでしょう?
私はムンバイ出身のインド生まれ、インド育ちですが、アメリカで大学教育を受け、カリフォルニア、ニューヨーク、パリなどで生活した経験もあることで、どこかインドに対してアウトサイダーでもある感覚があるのです。そしてその自分の感覚に忠実でありたいと思っていたので、美術監督はインド人ですが、撮影監督はあえてフランス人に依頼し、編集もフランスで行うなど、外側の視点を織り交ぜるようにしました。

ラストシーンが素晴らしかったです。ラトナがアシュヴィンに向けて発したたった一言が、ふたりが見る風景を大きく変えました。
そう感じてもらえてすごく嬉しいです。
次回作の構想はすでにあるのでしょうか?
いくつかアイデアはありますが、今はこの作品のために世界中を回っているので、アイデアを脚本に落とす時間がありません(笑)。ひとつはっきりしているのは、ラトナとアシュヴィンように自分が心から大切だと思える物語に自分が出会えなければ、その作品のために闘うこともできないということです。
最後になりますが、監督はこの作品を通じて初来日されましたが、日本の女性は監督の目にはどのように映りましたか?
来日する前は習慣や文化的な違いから、日本の皆さんはきっとクールでかなりフォーマルな感じなのかな?と、実は少し緊張していました。でも実際はその想像とは違っていて、みなさんとてもカジュアルで話しやすく、いつも心地よい環境を作ってくれました。何よりこの通り、強くて美しい女性に囲まれて仕事をしていたので(笑)、たくさん刺激を受けました。日本、またすぐ来たいです。

ロヘナ・ゲラ
1973年プネー生まれ。カリフォルニアのスタンフォード大学(学士号)と
ニューヨークのサラ・ローレンス大学(美術学修士号)で学ぶ。
1996年、パラマウント・ピクチャーズ文学部門でキャリアをスタート。
以降、助監督、脚本家、インディペンデント映画の製作/監督などを経験。
ブレイクスルー(ニューヨークに本部がある国際非営利団体)の広報責任者を務めたほか、
国連財団からインドでの自然保護キャンペーンの顧問に招待されるなど活躍は多岐にわたる。
Information
『あなたの名前を呼べたなら』
監督・脚本:ロヘナ・ゲラ
出演:ティロタマ・ショーム、ヴィヴェーク・ゴーンバル、ギータンジャリ・クルカルニー
公開:8月2日(金)Bunkamuraル・シネマほか全国順次公開
公式サイトはこちら