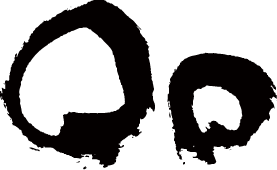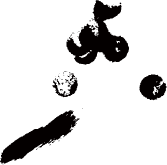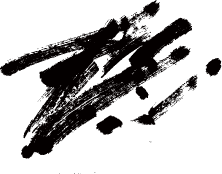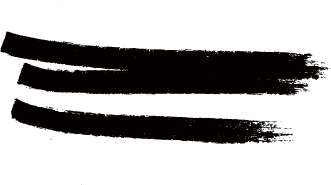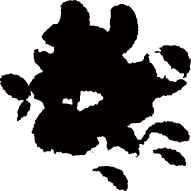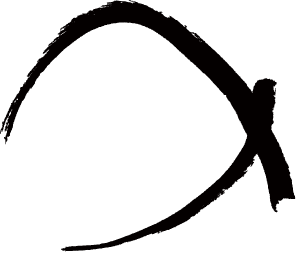新しいが本当に新しいのか?
先日、約3年の充電期間を経て、リニューアルオープンした東京都現代美術館。
まず、これまで当たり前に街にあった美術館の3年間の不在はとても寂しかった。近くを自転車で通るたびに今か今かと再オープンを楽しみにしていた。
東京都現代美術館があるあたりは、その昔、同潤会アパートの要塞のようなコンクリートの建物群が構成するエリアだった。今ではコーヒーを中心としたカルチャーの一大拠点となっており、当時とは街を歩く人々の様相も様変わりした。
東京都現代美術館がオープンした1995年は、1月に阪神淡路大震災、3月には地下鉄サリン事件、7月あのアマゾンがサービスを開始、8月にはマイクロソフトがwindows95(当時の新しいもの好きはウィンドウズを使っていた)を発表するなど、時代のひとつの転換点として記憶された年だ。
これまでさまざまな展覧会が開催されてきた。個人的に一番記憶に残っているがヴォルフガング・ティルマンスや、フランスのファッションデザイナー、マルタン・マルジェラが参加した1999年のエキシビション「身体の夢」。中庭に面したガラス窓を背にしたマルタン・マルジェラによるマネキンに着せられていた、バクテリアやカビなどの菌を塗布した変色して行くドレスの挑戦的なインスタレーションは今も目に鮮明に焼き付いている。そこには新しいものに価値を見いだすことに対する痛烈な批判精神があった。
さて、新生なった東京都現代美術館に足を踏み入れてまず驚いたのが、硬質な建築のなかに肌色の合板で造作したインフォメーションカンターや、これも肌色の円形のベンチ、大きめのサインが目に飛び込んできたこと。広々としたエントランスに点々と置かれていたふかふかのベンチがなくなっていたこと。それ以外は空間のレイアウトもモザイクタイルのトイレもそのまま。プログラムはファミリー層向けに舵が切られており、隣接する公園とのアプローチがより近くなったエントランスのしつらえにより、街との親和性が新設計の意図となっているようだ。
95年のオープンから約四半世紀が経ち、美術館の周囲にはピカピカのタワーマンションが建ち並ぶ。エントランスロビーの真新しい合板のスキンカラーも時とともにやわらかな飴色に変わっていくのだろうか?
個人的には美術館は街や人に開かれた存在であるべきだと考えている。これまでも十分開かれていたと思っているが、その意味でリニューアルした東京都現代美術館の方向性は期待をもっているし、さらにその設計の意図を考えてみたいと思っている。
夏には、こちらも約2年ぶりのTOKYO ART BOOK FAIR2019のこの場所での開催もアナウンスされた。さらにさまざまな可能性に開かれた場になることを楽しみにしたい。