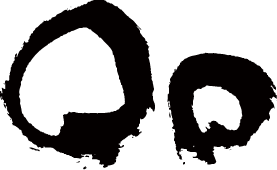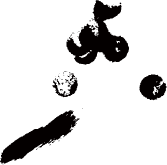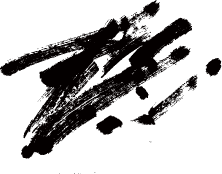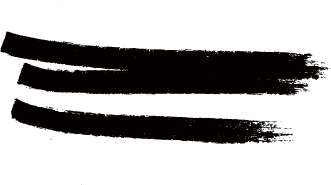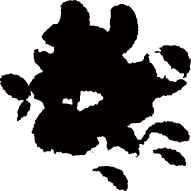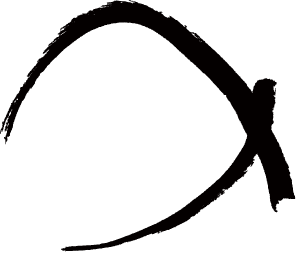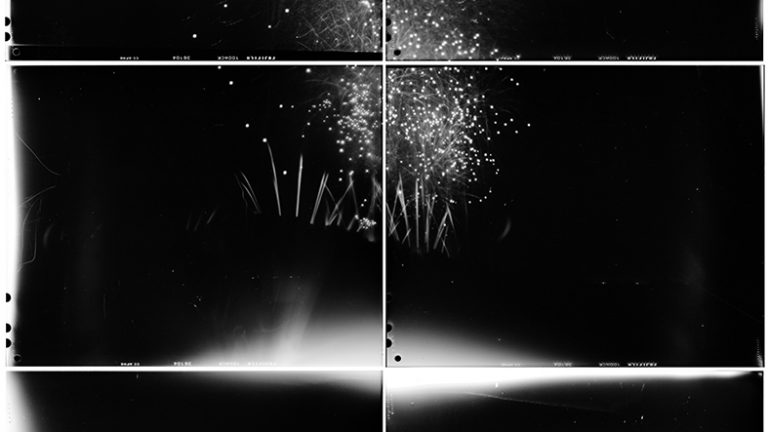022017
Special #15
映画から垣間見る、暮らしの心意気
人は皆、他者の中に自分を垣間見たり、他者の生き方を通じて世界を発見することがあります。
家族、友人、恋人、同僚など、他者と関わり続ける実生活は日々その繰り返しですが、
普段出会うことのない人間が生きている世界、映画もまた、私たちの人生の、暮らしの手がかりになることがありませんか?
今回はそんな映画を2作品、ご紹介したいと思います。
選んだ2作品に登場する人間は、国籍も職種も生きた時代も違います。
ただ共通しているのは、チャーミングであること、ささやかな日常の中にある喜び、豊かさを捉えられる人、テマヒマをかけて生きた人です。
これは合理性や機能性が求められるこの現代社会の中ではある種、こぼれ落ちているものかもしれません。
でもそんななかにこそ、ずっと心に据えておきたい大切なものが隠されているはず。
ぜひご縁があれば彼らの人生をのぞいてみてください。

1作目は現在全国各地で公開中の『人生フルーツ』。本作の主人公は、建築家の津端修一さんと妻の英子さん。日本モダニズムの巨匠アントニン・レーモンドに師事し、日本住宅公団のエースと呼ばれた修一さんは、自ら手がけた愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウン内に3000坪の土地を買い、家を建て、そこで約40年、家族で暮らしてきました。本作はそんな夫婦の日々の営みを、東海テレビが淡々と追ったドキュメンタリー映画です。
夫婦の1日は、とにかく忙しそうです。雑木林に囲まれた玄関のない30畳一間の母屋と、70種類の野菜と50種類の果物を育てる庭を行ったり来たりしながら、修一さんは友人・知人へのお礼状を毎日10通は綴り、英子さんは編み物から機織りまでこなします。桃のコンポート、ガトーショコラ、みたらしだんご。英子さんお手製のおやつの時間も欠かせません。
「自分ひとりでやれることを見つけてそれをコツコツやれば、時間はかかるけれど何か見えてくるから、とにかく自分でやること」。修一さんの価値観が夫婦の営みを作ってきました。


夫婦の原点は1960年にさかのぼります。当時、修一さんは風の通り道となる雑木林を残し、自然との共生を目指したニュータウンを計画していました。ところが時代の価値観は経済優先。山は削られ谷は埋められ、完成したのは、理想とはほど遠い無機質な大規模住宅だったのです。そんな修一さんが「ひとりでも里山の一部を作り出すことができるかと言う実験です」と建てたのが、今の夫婦が暮らす自邸でした。
合理性を求めて開発されていく都市の風景の傍らで、自分の心の声に耳を傾けながら、自分の中の自然に従って、人生を豊かにしてきた津端夫婦。長い歳月をかけて続けてきたこの「実験」が実を結び、物語の後半は90歳の修一さん、人生最後の仕事へと向かっていく姿を追いかけます。
情報に溢れたこの社会に生きる私たちは、時に他者の価値観に押し流されてしまいそうな日があります。そんなときこそ津端夫婦のように自分の手を動かしてやってみること。すぐに答えはでないかもしれないけれど、ふとした瞬間にいろんな物事が繋がって道が開けるかもしれません。『人生フルーツ』を合言葉にしながら。

2作目は『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』です。ソール・ライターは、1950年代からファッションカメラマンとしてニューヨークで活躍した写真家です。1980年代に入ると一度商業写真から退いたものの、2006年にドイツのシュタイデル社によって出版された作品集『Early Color』によって、再び世界から注目を浴びる存在になりました。
本作はそんな今は亡き彼の半生を追ったドキュメンタリー映画。2015年から日本各地でも公開されて話題を呼びましたが、嬉しいことにこの春(4月29日〜)からは渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで大規模な展覧会が決定しています。写真家としての彼の息遣いを生で観ることができるこの機会、絶対見逃せません。



映画の舞台はニューヨーク・イーストビレッジ。ライターはこの街に54年住んでいます。
「私は大した人間じゃない、映画にする価値なんかあるもんか。でもまあ仕方ないか……」。皮肉めいて語るライターのアパートは、膨大な資料と自身で描いた絵画、そして過去に撮りためた写真に埋もれていて、歩くにも一苦労の様子。部屋の窓辺には愛猫レモンの姿。そんなちょっと窮屈な部屋で、何かもごもごと言いながらうろついては、散らばっていた未発表ネガを拾い集めるライターが淡々と映し出されています。
「私が好きな写真は、一見何も写っていないようで、隅の方で何かが起きているような写真なんだ」。
基本的にカメラはお構いなしといった調子ですが、時折こちらにそのネガを見せてくれるライターの姿を追ううちに、まるで自分もその窮屈な部屋に入り込んで彼の隣で話しを聞いているような感覚に陥ります。
「有名人を撮るよりも、雨に濡れた窓を撮る方が私には興味深いんだ」。
90歳に近づいた彼が時折街に出て撮影するのは、そこに偶然通りかかった人や子供や猫や鳥、風景など。その全ては自宅から数ブロック圏内にあるものばかりです。そうやってライターは54年もの間、同じ場所に住み、シャッターを切り続けて来ました。

Canopy, 1958
©Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

Postmen, 1952
©Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

Sign Painter, 1954, 1954
©Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

Reflection, 1958
©Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

Soames Bantry, Nova, 1960
©Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.
どんなにドラマティックな展開を求めても、日常は避けて通ることはできません。ライターはそんな世界を肯定し、期待はしないけれどときめいる。そして、私たちは彼の撮った世界の断片を見ているうちに、これからも続いていくありふれた日常が、少しだけ気配を変えて近づいてくるのです。
「私の写真は、後ろから人の左耳をそっとくすぐるためにある」。
言い得て妙とはまさにこのこと。自身の写真の温度を的確に言葉でも表現したライターは、偏屈だけどどこか人懐っこくて、終始魅力に溢れた人でした。そしてごった返した自分の部屋で、「人生で大切なことは、何を手に入れるかじゃない。何を捨てるかということだ」とつぶやくのですが、それもまた妙に説得力があるのが、ライターなのです。
『人生フルーツ』そして『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』。変わりゆく時代のなか、自分の価値観に素直に心と身体を動かし続けた津端修一、英子夫妻とソール・ライターの生き方は、私たちの日常にときめきとユーモアを与えてくれます。