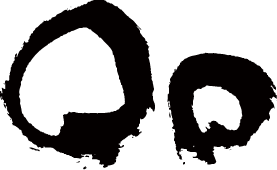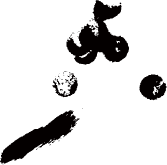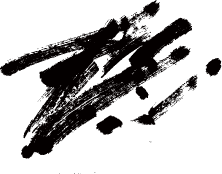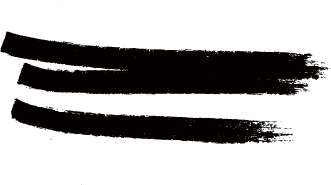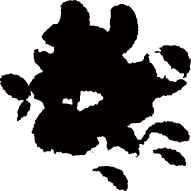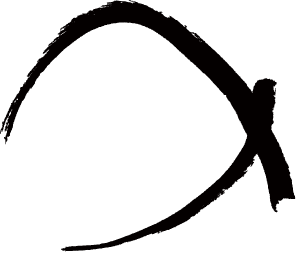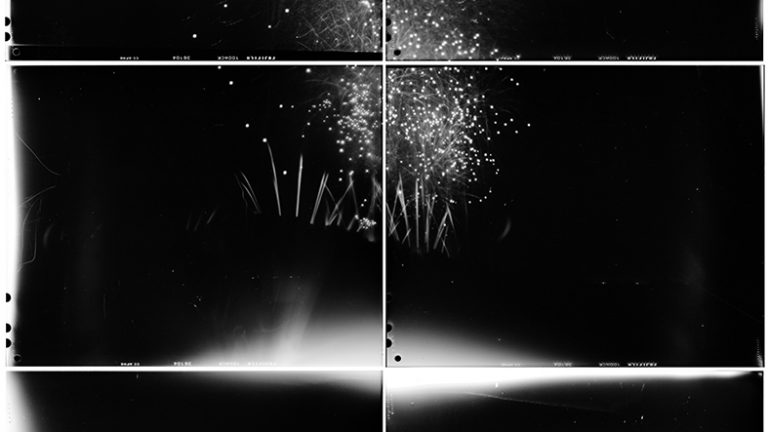092016
Special #13
継いでいく、日本人のこころ
金継ぎ師 山下裕子氏、グラフィックデザイナー清水将司氏インタビュー
加速していく便利で快適な現代の暮らし。
今や未来に焦点を当てていれば、
古い時代は遠い日の記憶、記録かもしれない。
けれど、時は確かにつながっていて、
過去から今へと、受け継いでいる知恵や技術がある。
そのひとつが、金継ぎと古布。
用の美が宿る日本の古い文化に魅了された二人の活動から、
豊潤な暮らしとは何か、その断片を紐解いていきます。
器のなかに見る、あたらしい景色
山下裕子(金継ぎ師)
山下 裕子
1975年島根県生まれ。ファッションブランドのプレスを経て、兼ねてから学んでいた漆芸の道へ。現在は漆で器を修繕する金継ぎ師として活動している。
「金継ぎ」とはその名の通り、割れたり欠けたりした器を金で継ぐものだと思っていましたが、漆で継ぐものなんですね。山下さんからそう伺ったとき、目から鱗のような気持ちになりました。
そうなんです。実は金や銀はその継いだところを最後に装飾するときに使うもので、実際に金継ぎとは、漆継ぎなんです。漆は塗料としてはよく知られていますが、実は接着力があって防虫効果もあるすごく丈夫な天然素材で、日本では古くからお寺といった貴重な建造物から武士が纏う鎧にまで漆が塗られていました。漆ってすごく長い歴史のなかでさまざまな技術が磨かれていきながら発展していったんです。
漆に接着力や防虫効果があるなんて全然知りませんでした。そもそも私たちの先祖はいつ、どんなときに漆の力を発見したんでしょうね。
きっかけはアシナガバチとの説があります。アシナガバチの巣に付着していた黒い液体が漆だったようなんです。要は漆の接着効果を利用してアシナガバチは巣を取り付けていたと。それを見た人間が「漆は接着剤になる」とひらめいて、それから矢を作るときに漆を使い始めたという逸話を聞いたことがあります。




それは面白い逸話ですね。金継ぎ自体の歴史はいつ頃から始まったんですか?
日本で茶の湯が盛んになった室町時代からです。当時、茶の湯は位の高い人たちの嗜みだったということあって、使う茶器も相当高価なものばかりでした。そんな貴重な器が例えば欠けて割れてしまったとしても、そう簡単に手放すことはできませんよね。きっと愛着も深いだろうし。「まだまだその器を使いたい」。当時の人々の想いに応える器の修復方法こそが、金継ぎだったんです。それも器の割れ目を隠すのではなくあえて金や銀で装飾するというのは、日本独自の美意識。割れて修繕した器の傷跡は「景色」と呼ぶんですよ。あたらしい景色を見る、楽しむ。それが金継ぎなんです。
「景色」。そう呼んだ日本人の感性がまた本当に粋ですね。そんな金継ぎの道に山下さんは何をきっかけに入ろうと思ったのですか?
5年ぐらい前にとても大切にしていた器が割れてしまったんです。でも割れてしまったからといってそのまま捨てるという考えには全然ならなくて。むしろ自分で直したい。だったら金継ぎで直そうと。金継ぎという修繕手法があることは知っていたので、この機会にちゃんと学ぼうと決めました。それがきっかけですね。
もともと金継ぎに興味があったんですか?
ありました。私は島根県松江市出身で20代後半までずっと松江で暮らしてきたんですけど、島根には不昧流という茶道の流派があるので、昔から茶の湯の文化が根付いている土地なんです。また島根は1920年代には柳宗悦が中心となった民藝運動の影響も強く受けているので、今も用の美を追求した陶器が作り継がれています。そういう街で私は生まれ育ったので、幼い頃からお茶や器の文化に触れるということが割と身近だったんですよね。そのせいも合って、器を見たり触ったりするのはずっと好きでした。金継ぎもまた、その延長線上で知っていたんです。
生まれ育った環境が、金継ぎ師になる道に山下さんを導いていったんですね。
でも実際、こんなに金継ぎに夢中になるとは想像していませんでした。3年前に金継ぎ教室に通おうと思った時も、最初はあくまで自分の器を直したいだけの趣味の範囲で考えていたんです。でも、実際に習い始めて、漆の奥深さにはまってしまって。それからですね、本格的に金継ぎの道に行こうと思ったのは。
漆の奥深さとはどんなところでしょうか?
例えば金継ぎに使う漆の種類はいろいろあるんですけど、ベースとして一番使うものは「生漆」と言います。その「生漆」は初夏から秋にかけて漆掻き職人さんが樹齢10年以上の漆の木から採取するんですけど、1本の木から採れる樹液(漆)がどのくらいかわかります? それが牛乳瓶一本ぐらいしか取れないんです。たったそれだけの量を限られた日に少しずつ採取して……、採取されたらその漆の木は伐採されるんです。それを知った時、本当にショックというか……、すごく責任を感じました。
漆の命を私たちは受け取っているんですね。
そうなんです。実際金継ぎをする過程の中でも、漆は生きているんだなあって思う瞬間が沢山あります。生漆は乳白色のミルクティーのような色をしているんですけど、空気に触れると酸化して、褐色になっていくんです。漆は湿度で硬化するので、繕った器を湿度を保った「室(ムロ)」で管理して、毎日漆の状態を見極めながら作業します。梅雨の時期が適していて、冬は寒くて乾燥するので、季節によってかかる時間も違うんです。とにかくすごく繊細なので、常に寄り添って生活してる感じがします。
最後に、金継ぎ師として大切にしていることを教えてください。
その器の素材を活かしながら、元の良さは絶対に損なわないように修繕することですね。その上で新しい景色を感じてもらえるように、よりその器に愛着を持っていただけるように。金継ぎを通してそのお手伝いをやっていきたいと思います。

金継ぎに使う道具は、生漆、黒呂色漆、弁柄漆などの漆類を始め、中力粉、砥の粉や木粉、金粉、銀粉、筆、竹べら、金属粉を磨くための鯛牙などが必需品になる。(写真左上)「生漆」は、その名の通り、生もののため冷蔵庫で保管する。(写真右上)仕上げに使う金粉や銀粉。粉末状のものが、専門店にて販売されている。(写真中央)金や銀を磨く際に使われる道具、鯛牙(たいき)。細い棒の先に鯛の歯がくくりつけてあり、この鯛牙で光沢がでるまで磨いていく。

古布に宿った私たちの生きる術
清水将司(イラストレーター・グラフィックデザイナー)
清水将司
1980年栃木生まれ。CI、カタログ、パッケージ、エディトリアル、アパレルなどグラフィックを中心に、現在栃木と東京2拠点で活動。著書に絵本『みんなでさがそう どこどこかくれんぼ』(コスミック出版)がある。gaimgraphics所属。
清水さんは同じデザイナー仲間とオンラインシショップLIKE THIS SHOPを運営しています。このショップではこれまでの価値観とこれからの豊かさを見つめた上で、自分たちが「LIKE THIS」と呼べるものをセレクトして販売していますが、ショップを立ち上げたきっかけから教えてください。
僕はgaimgraphicsというグラフィック集団に所属しているんですが、今年が会社設立11年目になるんですね。なんとか10年やってくることができて、11年目に入った今、改めて自分たちでゼロから何かを始めたい、発信していきたいと思ったんです。ただ、ものが溢れるこの時代に、安易に自分たちのエゴだけで何かを作り出すことはしたくない。としたときにじゃあ何ができるのかを自分たちなりに真っすぐ突き詰めた結果、この島の気候と文化と技術に基づきながら、自分たちの暮らしや遊びの中で使いたいものを納得がいくまで手を動かしながらかたちにしていこうと思ったんです。
そのひとつの結果として、LIKE THIS SHOPで清水さんは主に古布を使ったポケットTシャツをディレクションしていますよね。
ここ数年、骨董市で個人的に買い集めていた古布があってそれを「古布はポテンシャルがすごく高いと思っている」って仲間に見せたら、「これはやばい」と想像以上にみんなが好反応を示してくれたんです。そこからですね。古布の可能性を具体的にかたちにしていこうと思ったのは。それで仲間と話をして古布を使ったTシャツを作ることにしたんです。


古布は主に骨董市で集めているという清水さん。「よく行くのは北関東最大の骨董市、栃木の大前神社骨董市。毎回宝探し気分を味わっています」。(写真上)清水さんの古布コレクションの一部。左奥の玉になっている古布の正体は、昔の人が野良着の下に履いていたという股引きのひも。「使い道がないなあと思っていた大量のひもを三つ編みにして巻いたところ、結構かっこいいオブジェのようになりました(笑)」。(写真下)はぎれだけでなく、比較的状態の良い野良着や半纏なども集めている。「当時、生活の中で必要に迫られて作られた日常着ですが、この時代にファッションの視点から見てもすごく魅力的に思えるんです」


(写真上)心も体も気持ちよく、長く着れるTシャツを目指した結果、日本製に拘ったオリジナルのボディーで制作している。自然と触れ合うことが大好きなLIKE THIS SHOPチームは、環境へのインパクトなども考慮し、糸はフェアトレードされているオーガニックコットンを使用。織りは現在絶滅寸前の国内の吊り編み機を使い、ゆっくり時間をかけて編み上げる丸胴仕上げに。ふんわりした風合いにが体によく馴染む。(写真下)タグのデザインは清水さん自身のによるもの。このTシャツを始めLIKE THIS SHOPのアイテムは、全て顔の見える小さな単位で丁寧な制作を心がけている。
古布のポテンシャルとは、具体的にどんな部分に感じたのですか?
色々あるんですけど、一番は一つ一つに違いがあって、同じものがないところです。だから骨董市でもひたすら宝探しをする感覚なんです。そもそも日本は綿がほとんど育たない土地だったので、麻が主流の時代がすごく長かったんです。それが江戸時代初期に海外から綿が輸入され始めると、少しずつ大阪から関東へ運ばれ、そして全国に普及されていって。普及が浸透するまでは、特に東北では木綿は貴重なものとして扱われていました。例えば青森で有名な刺し子と呼ばれる野良着がありますが、これは目が荒く冷たい風を通してしまう麻の野良着の隙間に、木綿糸を編みこんだものなんですね。わずかの木綿糸を効果的に使うことで、寒風から身を守る。つまり刺し子は木綿が貴重だった時代に生まれた庶民の生活の知恵だったんです。
誰かに見せるためのものではなく、あくまで生活の必要に迫られて生まれたものなんですね。
そうなんです。古布にはものを大切にしてきた日本人の生き方のようなものが宿っている。僕は古布のそんなところにとても惹かれました。最近、刺し子野良着は海外でも人気がすごく高いんです。向こうの人は手に入れた野良着を家で飾るんです。つまり野良着がアート作品に。面白いですよね。当時の日本人の生活そのものが、アート作品として飾られる時代が来るなんて。
清水さんが収集している古布はどの時代のものが多いのですか?
主に明治以降から戦前のものですね。その古布がいつの時代のものなのかは、糸の太さ、細さ、種類である程度はわかってきます。あと、当時の染めは草木染めなんですよ。化学染料が海外から日本に入る明治の30年頃以前まで、布はすべて草木などの天然の染料で染められていたんです。僕はその化学染料が入ってくるちょうどその狭間の、日本が文明開化する過程の古布を持っています。色はすべて藍色。もともと藍色は一部の特権階級の人のみに許された色だったんですが、その藍の青色が庶民の色となったのは江戸中期のこと。野良着のように、生活に根ざした藍色が僕は好きなんです。
古布との付き合いのなかで、清水さんが一番うれしい瞬間とはどんなときですか?
骨董市で買った古布を自宅に持ち帰って洗濯をした後にアイロンがけしている時がすごく幸せなんですよね。というのも骨董市では古布はくしゃくしゃになっていたりするものも多くて意外とその古布の実態がよくわからないものも多いんですよ。それを一通り洗濯してアイロンを掛けていくと、布のクオリティーがはっきりとしてくるんです。その瞬間がすごく好きなんですね。そんな話を僕が尊敬している青山にある古民芸のもりたさんにしたら「わかる!」って言ってくれました(笑)。

古布を使ったものづくりも、LIKE THIS SHOPも始まったばかりです。最後に今後の展開について教えてください。
変わらず骨董市に通いながら、古布についてはもっと勉強したいですね。骨董市に出店している骨董屋の方たちが年齢層も高く知識が深いのでその方たちに色々と相談しながら、知識を深めていきたいです。平行してLIKE THIS SHOPでは、古布シリーズ第二弾の新作を作っています。今サンプルがあがってくる段階なのですが、完成したらウェブショップで販売するので是非見てみてください。ゆっくりペースにはなってしまうのですが、今後も自分たちが納得のいくものづくりをしていきたいですね。そしてそのものが生まれる背景に対してもしっかり筋を通していきたい。それも丁寧に。そこだけはぶれずにやっていきたいです。