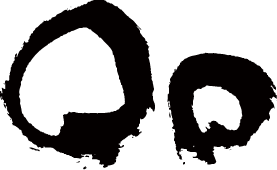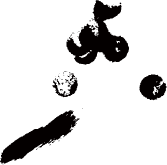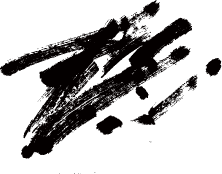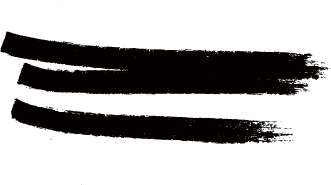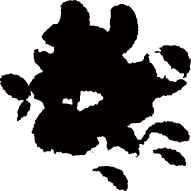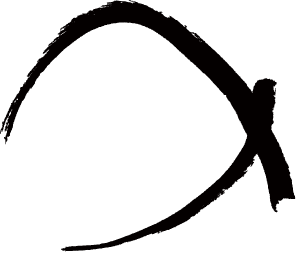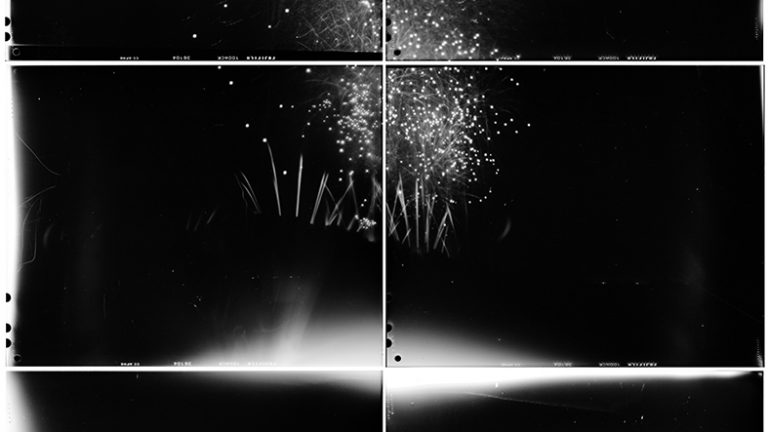122017
Special #22
サウダージ 〜アルヴァロ・シザの建築
5年ぶりのヨーロッパは、ポルトガルとスペインへ。旅のテーマは、アルヴァロ・シザの建築とスペイン・ロマネスクを訪ねる旅。
かけがえのない旅の日々、なかでも最も多くの時間を割いて巡ったのは、シザの建築だった。
日本から遠い国、ポルトガル。だけど心の距離はぐっと近くなった。そのふくよかな体験について、少しでも共有できればと思う。

ポルトガル第二の都市、ポルトの街全景。右に見えるのは、1886年建造のドン・ルイス1世橋。上は路面電車、下は自動車が走って家、どちらも歩いて渡れる。
旅のきっかけは、銀座の画廊から
今回、私がポルトガルとスペイン取材旅に行くきっかけを作ってくれたのは、銀座の画廊、巷房オーナーの東崎さんだった。
私は巷房が好きだ。巷房は1932年に施工され、今も昔も芸術家たちに愛される奥野ビルの中にある。その当時は高級アパートだった奥野ビル。民間の建物としては日本で初めて手動式エレベーターを備えたビルとしても有名で、80年以上経った今も現役で訪れる人たちの足になっている。
そもそも東崎さんとの出会いは、敬愛するグラフィックデザイナー佐藤卓さんの個展で、巷房の扉を開いたことだった。凛とした白い空間に、小さな人間型ロボットがひそやかに歩いている。ソーラーパネルから得られるわずかなエネルギーでロボットは歩いていた。自然光の入る3階の会場では太陽を、地下の会場では電気を光源に歩くこのロボットを題材にした佐藤さんの個展は、『光で歩く人』と名づけられていた。巷房という空間でしかできないこと、できること。『光で歩く人』はそういう展示だった。
展示を観ながら一瞬で巷房という空間に魅せられた私は、その後もときどき足を運びながら、東崎さんと会話をするようになる。雑誌で巷房の取材させていただくこともあった。やがて私の狭い文脈では到底出合えなかった美術や写真のことを東崎さんに教わるようになっていた。

今回の旅の出発点となったポルトガル第二の都市・ポルトの市民の台所ボリャオン市場。その歴史は180年以上と長い。
そんな東崎さんに、ある日旅に誘われた。旅のテーマは、シザの建築とロマネスク様式を訪ねる、スペイン・ポルトガルの旅。シザとはポルトガルを代表する建築家で、しばしば建築界のノーベル賞と称されるプリツカー賞や高松宮殿下記念世界文化賞など、数々の賞を受賞しているアルヴァロ・シザのこと。そしてロマネスクとは、10世紀後半から13世紀中頃にかけてフランス、イタリア、スペイン、ドイツを中心に西欧諸国で見られた建築と美術様式のことを表している。修道院の建築様式として発達したものが多いロマネスク建築は、厚い壁と小さな窓、円形アーチが特徴で、装飾も少なく、禁欲の場である修道院の振る舞いがじかに感じられる。

スペイン・レオンよりアストゥリアス地方の街、オヴィエドの郊外にある世界遺産、サンタ・マリア・デル・ナランコ教会の中からの眺め。
と、こんな風に調べればすぐにある程度の知識は得られるけれど、私はそれまで恥ずかしいことにアルヴァロ・シザを知らなかった。ロマネスク様式についても、過去、フランスやイタリアに訪れた際に観てはいるものの、正直、自分にとってのフィジカルな体験にはなっていなかったように思う。
だけど、東崎さんに誘われた瞬間から私はこの旅に心を掴まれていた。結局、世界とは見かたひとつで大きく変わる。どの視点に立つか、どんな文脈を辿るかで、世界は変わる。その前提に立ったとき、私は巷房を通して触れる東崎さんの視点や感性に多くの刺激を受けていた身。東崎さんがアレンジしながら出来上がったスペイン・ポルトガルの旅であるなら、きっと新しい世界を体験できる。そう確信していた。
こうして私は、11月3日から13日までの11日間、ポルトガル・ポルトから、スペイン・トレドまでをバスで移動しながら旅をした。1日、1日濃密な時間を過ごし、今もその11日間の旅を反芻する毎日だけれど、なかでも私にとって特にかけがえのない出合いはやはり、アルヴァロ・シザの建築。いや正しくは建築を通じて触れたシザの信念だったように思う。

スペインで最も美しいと言われているロマネスク様式の回廊があるサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院。北スペイン、ブルゴスから足をのばした山間にある。

海へと続くスイミングプール
私が初対面したシザの作品は、初期の代表作と言われているレサのスイミングプール(以下市民プール)だった。ポルトガル北部の港湾都市で リスボンに次ぐポルトガル第二の都市、ポルト。その郊外に位置する港町、マトジーニョスにあるこの市民プールは、海岸の岩場の一部を活かして造られた屋外プールで、夏になると今も子供からお年寄りまで、地元の人たちを中心に多くの人たちで賑わっている。
大西洋の海岸線を走るリベルダーデ通りにバスを停めて、市民プールのある場所へと徒歩で向かう。その外観は想像以上に、ひそやかだった。海への眺望を遮らないように、建物の外観は道路面より低く抑えて設計されている。そのため、入り口はスロープによって屋根の下の空間に潜り込んでいくような動線になっていた。築50年以上経つコンクリートが風化して自然の岩場とほどよく同化しながら、海にそのまま連続している。けれど、すぐに海は見せない。必要なところに擁壁が配置していた。


プールは子供用と大人用がある。写真は大人用のプールで深いところで水深が4メートルもある。そしてプールの水は海水を利用している。
私はこの擁壁にぐっと心を掴まれた。
音楽でも舞台でも、優れた作品を見ると、いつも時間と空間が伸び縮みしているような感覚に襲われる。アインシュタインの相対性理論のように。市民プールの場合、まさにこの擁壁がその役割を担っていて、すごく魅力的に時間と空間を操っているように思えた。夏の風景も見てみたいし、できれば地元の人たちと一緒にここで泳いでみたい。そんな思いにかられながら、市民プールからほど近い岬に建つレストラン、ボア・ノヴァのティーハウス&レストランへ。ここもまた、シザによる設計だった。シザの最初のプロジェクト(1963年)であり、本人の手でこれまで改装が行われてきたと言う。
そして私はそのレストランに隣接する小さな教会(写真右)に目がいった。小さく素朴で、慎ましやかな振る舞いをしたその教会は、ポルトガルの人々のシャイで暖かな人柄と重なって見えた。
このマトジーニョスという街は、シザの生誕地でもある。


その土地の風土と建築の、心地よい共存
「壁」といえば、セラルヴェス財団が所有する広大な敷地の一角にあるセラルヴェス現代美術館(写真上下右)もまた、シザの代表作(1999年)のひとつであり、私が今回の旅で深くしびれた建築でもある。
国内外の多様な現代アートを展示・収蔵し、館内には図書館や劇場も併設されているセラルヴェス現代美術館。真っ白い壁面に反射する自然光のコントラストが美しい小さなエントランスからは、美術館の全体像はつかめない。シザの建築は開口部が最小限に留められていて、一見、とても内向きな空間であるように映るところが一つの特徴だと思う。けれど歩くに従って少しずつひらかれていく空間のストーリーが言葉にならないぐらい魅力的で、それは先のレサのスイミングプールとも通じるものがある。

その土地の歴史や風土、人の営みが培っていた文脈と、シザの建築的思想としての文脈。ふたつの独立した文脈がごく自然に共存する風景を、私はセラルヴェスでじっくりと眺めた。それは本当に美しい風景であり、どこか気の利いたユーモアも、その風景から感じ取る。改めて、私はシザが好きだと実感した。
シザの主な代表作の解説や紹介を始め、シザのインタビュー記事などが掲載されている『アルヴァロ・シザの建築』(TOTO出版)の冒頭ページには、「建築:始めるー終える」と題した建築にまつわるシザ自身による序文が綴られている。実に旨味のある文章なので、一部抜粋して紹介したい。

森、そして美しい芝生が広がっている敷地内には現代アートも点在。セラルヴェス現代美術館はその豊かな緑と調和しながら存在している。

3.望まれた高さまで建ち上げられた壁を初めて目にすること。その内部に居ることを自覚し、遠くから眺める。記憶の中にある全体像の断片が連続する様を吟味しながら、敷地を歩む。自分を取り巻く物資を見て、その先を視る。開口と、それが明らかにしてくれるものとの繋がりを見いだす。存在しないドアをこちらの角度から、そしてまた別の角度から入ること。
この家で営まれることになる人生の一日を瞬時に想像してみること。その家庭を満たすであろう出会いとすれ違い、悦びと痛み、疲労と活力、受け入れられた退屈と熱狂、魅惑と無関心を無視せずに。
『アルヴァロ・シザの建築』(TOTO出版)の「建築:始めるー終える」より抜粋

世界中から建築巡礼者が訪れる、マルコ・デ・カナヴェーゼス教会。
時折必要なエスケープ
シザを語る上で、重要なエレメンツのひとつにドローイングがある。シザは何度も繰り返しながら、建築や空間のイメージを描いていく。と同時にそのなかには設計に関係のない、馬や天使のドローイングもある。思いのままに筆を走らせたであろうその数々は、どれも有機的でチャーミングで、本当に風通しが良い。実際、ドローイングのみを紹介した本も出版されているほど、ファンは多く、私も今回深く印象に残ったドローイングがある。
「スケッチしたり、絵を描いたりすることは、本当に自由で開放的なことなので、些細だけれど頑固な問題から少し逃避して、夢を見ることができるというわけなのです」。(『アルヴァロ・シザの建築』(TOTO出版)アルヴァロ・シザ インタビューより一部抜粋)

彼にとってドローイングとは「時折必要なエスケープ」だった、とも同誌で語られていたが、私はこの旅でそのエスケープに真正面から心射抜かれてしまった。<マルコ・デ・カナヴェーゼス教会>の吹き抜けをふいに見上げたときの、あの言語化できない感触は、今も私の心にまとわりつついている。
4.数カ月後に、覆われた空間と開かれた空間をまわること。密度、整列、分裂や、時間の気まぐれによって抑えられたり解き放たれたりする光を鑑賞すること。
『アルヴァロ・シザの建築』(TOTO出版)の「建築:始めるー終える」より抜粋
ポルトの街から内陸に約1時間30分ほどバスを走らせると、マルコ・デ・カナベセスという小さな街にたどり着く。その街の丘の上に建つ教会、<マルコ・デ・カナヴェーゼス教会>は、この街のシンボルでシザが設計したものだ。
私たちがこの教会にたどり着いたときは、ちょうどミサの時間が始まる直前だった。地元の人たちがぞろぞろと巨大なエントランス扉の中に入っていく。その列に並び、内部へと入ってみると、私は静かに高揚した。外からはシンメトリーに突き出た凹字型の箱のように見えたその教会の内部は、建物の質が一変するほど多様な表情を持っていた。アシンメトリーの光と影が空間のなかで戯れている。
ミサは始まり、私は入り口を背に左側の奥にある洗礼室の方へとそっと向かった。吹き抜けになっている洗礼室で、私は不意に天井を見上げた。するとその上部のタイルにはシザのドローイングが、キリストの身体と祝福を受ける者の身体が描かれている。言葉にでできない想いが心に充満する。なんと崇高な空間なんだろう。空間もドローイングも、そしてこの場所に集う人々の心も本当に美しく、ふいに涙が溢れそうになった。

素晴らしき師弟関係
もうひとつ、あたたかな気持ちをもらったドローイングがある。それはポルトガル・プラガ近郊の田舎町、サンタ・マリア・ド・ボウロにある修道院を改装したホテル、ポサーダ デ アマレス(写真上下右)でのこと。そもそもポサーダとは、古い城や修道院、貴族の屋敷などといった歴史的価値のある建造物を改築し、運営を行っているホテルの総称で、ポルトガルにはそんなポサーダという国営のホテルが約30軒近くある。新陳代謝の激しい東京では考えにくいこの取り組みは、本当に素晴らしいと思う。





上写真5枚ともに、ポサーダ デ アマレスの外観と内観。1997年に開業し、2009年に改装される。
ポサーダ デ アマレスは、もとは12世紀に建てられたシトー派の女子修道院だったものを、シザの元弟子で同じくポルトガルの名建築家、エドゥアルド・ソウト・デ・モウラが、1987年から1997年までの約10年間をかけてホテルに改修していた。ホテルの隣の教会は今も現役で、地元の人たちの姿や営みがごく普通に垣間見れる。

教会の中の一室。

ポサーダ デ アマレス。は山奥の田舎町にあるため、夜は街灯も少なく、ホテル横の教会の明かりが周辺を包んでいる。その明かりのもと、地元の少年たちがサッカーをしていた。
筆舌に尽くしがたい素晴らしきこのホテルに、運良く2泊も宿泊させてもらったのだけれど、宿泊する部屋の一室には、シザのドローイング。さらに1Fの男女の共同トイレの両脇の壁に飾ってあるドローイング(写真右)もシザによるものだった。軽やかなドローイングは、トイレの男女を示していたのだ。なんて粋な計らいなのだろう。空間に対して主張せず、ささやかなところがまたぐっとくる。
6.飛行し、視界が届くものすべては本体に属していると、そして同時にその本体はすべてによって所有されているのだと認識すること。侵入者の正反対。見えないもの、既に見えなくなったものを含めること。
『アルヴァロ・シザの建築』(TOTO出版)の「建築:始めるー終える」より抜粋

その後もシザ、そしてモウラによる建築を巡る旅は続く。
ふたりが新築と改修を手がけた国際現代彫刻美術館とアバデ・ペドロサ市営博物館。モウラ設計による市営のサッカースタジアムブラガ ムニシパルスタジアム、そして国境を渡ってスペインではガリシア現代美術センターを見学。どれも語り尽くせない興奮が、今も心を熱くする。シザとモウラという2人の建築家を通して、ポルトガルの風景を知れて本当に良かった。


アヴェ川の谷間にある街、サント・ティルソにある国際現代彫刻美術館とアバデ・ペドロサ市営博物館の入り口。

国際現代彫刻美術館での展示風景。

市営博物館はサン・ベント修道院を改装して生まれた。


モウラの代表作としても名高いブラガ ムニシパルスタジアム。2004年、UEFA欧州選手権開催にあわせて作られた市営スタジアムは、現在、SCブラガがホームスタジアムとして使っている。もともと採石場のあった場所をサッカースタジアムに改造したもので、一方のゴールの後方には大きな岩盤の崖があり、もう一方は市街に向けてひらけているという一風変わったスタジアム。


スペイン東北部ガリシア地方の町、サンティアゴ・デ・コンポステーラにあるガリシア美術センターは休館のため、残念ながら中の見学できなかった。花崗岩に覆われた外観がとても印象的。美術センターはサント・ドミンゴ・デ・ボナバル修道院の敷地内に建てられていて、写真のように修道院と美術館の間の庭園が美しく、シザらしさを感じた。
ポルトガルは日本が初めて出会った西洋の国だった。1543年、九州の南に浮かぶ種子島に、ポルトガル商人が乗った1隻の船が漂着したときから、両国の交流は続く。こうしてポルトガルに実際に来てみて、日本にいるときのようにどこかほっと和むのも、両国の長い交流を思えばすとんと腑に落ちる。
サウダージ(saudade)。郷愁や切なさなど、一言で言い表せない多面的な意味合いを持つポルトガルの言葉は、ポサーダ デ アマレスの中庭から望む夕陽にぴったりだった。またいつか訪れるその日まで。